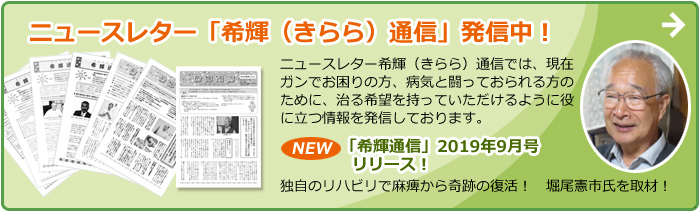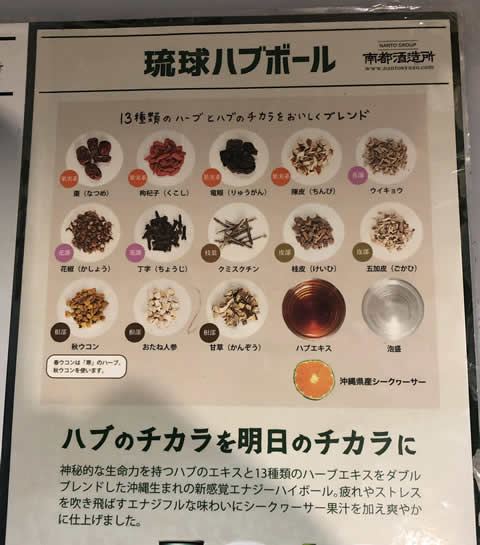去年に取材した掘尾さんの取材記事をようやくきらら通信で紹介する事が出来ました。堀尾さんは、脳出血により、半身麻痺をリハビリを自己流で行い、克服されてた方です。堀尾さんの所に通っていた方の話で印象に残っている話ですが、何かのセレモニー中に、いきなり寄ってこられて、車いすの横にきて、「良くなるよ!」と堀尾さんが声をかけたそうです。
私は、どんな時も困っている人を見たら、歩み寄り、話しかけるそのあり方がすごい!と思いました。しかも堀尾さんは、ボランティアでリハビリを教えているのです。その声をかけられた方は、堀尾さんに連絡をして猛練習をし、私に歩いている姿を見せてくれました。人の出会いによって大きく変わったのです。そんな内容も掲載しています。
以前に遅くまで面接した方が、サービス管理責任者の経験があるという事でしっかりその部分を確認しなかったのですが、その方が当社を選んでくれました。そして、申請をしようと思ったときに確認すると、今年から色々と状況が変わり、必ず研修を受けないといけない要件がある事がわかりました。
そんな事があったので、いろんな方に電話をしたり、紹介をしてもらっていました。中には、ずっと障害をお持ちの方の介護に携わっている方で、パートナーと会社を立ち上げ、その方は体を壊して入院。入院している時もご利用者さんと連絡を取り合ったりで、とっても気になるとの事。そして、入院中に会社の方向が変わり、自分でたちあげた会社を退いたのです。
医者にはまだ安静にした方が良いいと言われているのですが、前から関わっている必要としてくれるご利用者さんが待っているという事で、会社をあらたに作る準備をされている方がいらっしゃいました。ほんとすごいです。
1年前に箕面のまちゼミに来てくれた方で、きららリハビリ訪問看護ステーションと関連するお仕事をされていたので、とっても印象に残った方がいました。今までに電話をした事がなかったのですが、初めてお会いして1年経過してますが、電話をしてみました。
すると、覚えて頂き、最近の仕事での状況などをお聞きして、サービス管理責任者を探している事をお伝えすると、すでに箕面市で障害者のグループホームをされている方をご紹介してくださいました。
またこの方がとても良い方で、現在、3棟されていて、お話を聞きに行った時には、資料まで用意して頂き、たくさん資料を頂き、なんでも教えてくれました。しかも、この方は、物件を探しているときに、建っている家を見つけて、建っている時にオーナーに色々と交渉をして、デザインの変更などもしてもらい、家を借りているとの事。
これだけ聞けばついている人で終わるのですが、この方は、入居を希望する方と一緒にどんな所に住み、どんな所が良いのか?その入居を希望される方と一緒になって家を探し、一緒になって、あいさつ周りもしたと教えてくれました。そのやり続けた結果なのです。
しかも、その事業をさられるきっかけは、困っている方がいて助けたい!と思ったから、起業したのです。
みなさんの仕事に対する、目的がとてもすばらしいです。
世の中には自分のことよりも人の力になりたい!役に立ちたい!と思う方が近くにいるのです。
私も何かに挑戦したい気落ちの一つに今までに関わったお客さんの影響があります。
話は変わりますが、試作に試作を重ねた玉ねぎドレッシングも出来ました!子供がこのドレッシングを飲んだりもします。玉ねぎは、私達が作った無農薬・無化学肥料・無除草剤のタマネギを使っています。箕面ビールさんからわけてもらっている麦粕やタヒボジャパンのタヒボ茶殻を土に入れ、さらにドレッシングにはバイオノーマライザーを入れました。
自信をもってお勧めできるドレッシングです。畑で作った加工品第1号で初めてです。
昨日は、9時?18時40分まで畑仕事。今日も10時半?15時半まで畑仕事です。来年の為に、雑草を刈り、土を耕し、玉ねぎの種まきを行いました。ドレッシング以外にもポタージュも試作で美味しいのが完成して、玉ねぎが足らなかった状況でしたので、去年は玉葱を1万個作りましたが、今年は1万1000個ぐらいつくれたらと考えています。
人は何かの理由・目的があり動いています。そこで共感出来たり、学びあったりできるのは何かのご縁だとつくづく思った1週間でした。
堀尾さんを掲載した希輝通信(きららつうしん)ニュースレターを無料で配布しています。詳しくはこちら http://gankokuhuku.com/kirara-list/