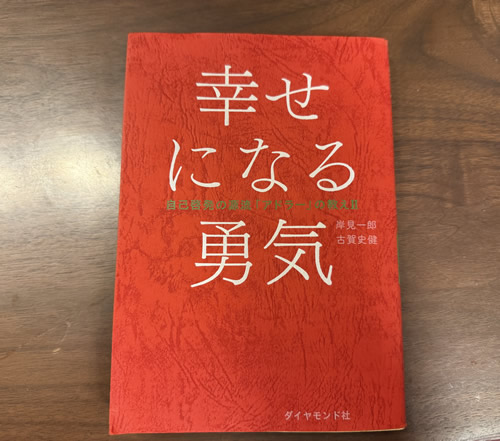幸せになる勇気という本を読んでいました。アドラー心理学の教えをもとに書いてある本で、印象に残る部分のみLINE(ライン)で撮影して文字お越しをして、記録していました。ちょうどこの本を読んでいる時に社内で参考になるような事もあったのでとってもタイミングが良かったのです。
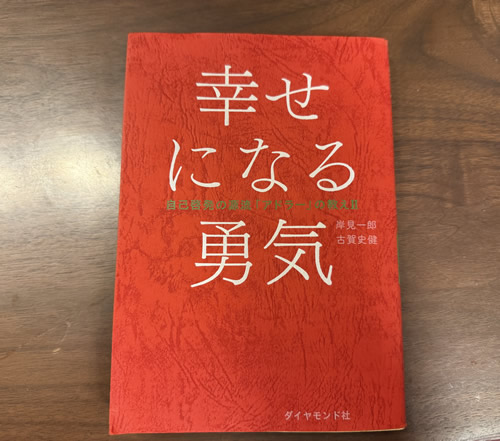
ここから本から抜粋した部分・・・・・・・・・・
人間は、過去の「原因」に突き動かされる存在ではなく、現在の「目的」に沿って生きているのだから。たとえば、「家庭環境が悪かったから、暗い性格になった」と語る人。これは人生の嘘である。ほんとうは「他者と関わることで、傷つきたくない」という目的が先にあり、その目的をかなえるために、誰とも関わらない「暗い性格」を選択する。そして自分がこんな性格を選んだ言い訳として、「過去の家庭環境」を持ち出している。つまり、われわれは過去の出来事によって決定される存在ではなく、その出来事に対して「どのような意味を与えるか」によって、自らの生を決定している。
これまでの人生にどんなことがあったとしても、これからの人生をどう生きるかについて、なんら関係がない。自分の人生を決定するのは、「いま、ここ」を生きるあなたなのだ。⋯
アドラーの思想は「人間は、いつでも自己を決定できる存在である」という、人間の尊厳と、人間が持つ可能性への強い信頼に基づいています。
自分を変えるとは、「それまでの自分」に見切りをつけ、「それまでの自分」を否定し
「それまでの自分」が二度と顔を出さないよう、「あたらしい自分」として生まれ変わるのでは、いくら現状に不満があるとはいえ、底の見えない闇に身を投げることができるのか。⋯⋯これは、そう簡単な話ではありません。
だから人は変わろうとしないし、どんなに苦しくとも「このままでいいんだ」と思いたい。そして現状を肯定するための、「このままでいい」材料を探しながら生きることになるのです。
「悪いあの人」の話を聞き、「かわいそうなわたし」の話を聞き、わたしが「それはつらかったね」とか「あなたはなにも悪くないよ」と同調すれば、ひとときの癒やしは得られるでしょう。カウンセリングを受けてよかった、この人に相談してよかった、という満足感もあるかもしれません。でも、それで明日からの毎日がどう変わるのか? また傷ついたら癒やしを求めたくなるので けっきょくそれは「依存」ではないのか?⋯⋯⋯だからこそアドラー心理学では「これからどうするか」を語り合うのです。
われわれ人間は、未熟な状態から成長していかなければならない、という原点に立ち返るのです。考えるべきは「これからどうするか」なのです。
あなたはいま、わたしの目の前にいるのです。「目の前にいるあなた」を知れば十分ですし、原理的にわたしは「過去のあなた」など知りようがありません。あなたが語る過去は、「いまのあなた」によって巧妙に編纂された物語にすぎない。
最終的な目標は、合意の形成です。伝えるだけでは意味がなく、伝えた内容が理解され、一定の合意を取りつけたとき、はじめてコミュニケーションは意味を持つ。
ルールを破れば厳しく闘せられ、ルールに従えばほめられる。そして承認される。つまり人々は、リーダーの人格や思想信条を支持しているのではなく、ただ「ほめられること」や「叱られないこと」を目的として、従っているのです。
アドラーは賞罰を禁じる。叱ってはいけない、ほめてもいけない、と断じる
アドラー心理学の提唱する「機の関係」を貫くのは、協力原理です。誰とも競争することなく、勝ちも負けも存在しない。他者とのあいだに知識や経験、また能力の違いがあってもかまわない。学業の成績、仕事の成果に関係なく、すべての人は対等であり、他者と協力することにこそ共同体をつくる意味がある。
人間はひとりでは生きていけないのです。孤独に耐えられないとか、話し相手がほしいとかいう以前に、生存のレベルで生きていけない。そして他者と「分業」するためには、その人のことを信じなければならない。疑っている相手とは、協力することができない。その人が好きだから協力するのではなく、香が応でも協力せざるをえない関係。そう考えてもらうといいでしょう。
運動競技のチームメイトなどは、典型的な分業の関係と言えるでしょう。試合に勝つためには、個人的な好悪を超えて協力せざるをえない。嫌いだから無視をするとか、仲が悪いから欠場するとか、そういった選択肢はありえない。試合が始まってしまえば、「好き」も「嫌い」も忘れてしまう。チームメイトのことを「友人」としてではなく、「機能」のひとつとして判断する。そして自分自身も、機能のひとつとして
「人の価値は、共同体において割り当てられる分業の役割を、どのように果たすかによって決められる」と。つまり、人間の価値は、「どんな仕事に従事するか」によって決まるのではない。その仕事に「どのような態度で取り組むか」によって決まるのだと。
企業の採用にあたっても、能力の高さが判断基準になる。これは間違いありません。しかし、分業をはじめてからの人物評価、また関係のあり方については、能力だけで判断されるものではない。むしろ「この人と一緒に働きたいか?」が大切になってくる。そうでないと、互いに助け合うことはむずかしくなりますからね。そうした「この人と一緒に働きたいか?」「この人が困ったとき、助けたいか?」を決める最大の要因は、その人の誠実さであり、仕事に取り組む態度なのです。
他者を信じること。これはなにかを鵜呑みにする、受動的な行為ではありません。ほんとうの信頼とは、どこまでも能動的な働きかけなのです。
「わたし」の幸せを優先させず、「あなた」の幸せだけに満足しない。「わたしたち」のふたりが幸せでなければ意味がない。「ふたりで成し遂げる課題」とは、そういうことです。
運命とは、自らの手でつくり上げるものなのです。われわれは運命の下僕になってはいけない。運命の主人であらねばならない。運命の人を求めるのではなく、運命といえるだけの関係を築き上げるのです。
ここまで本から抜粋した部分・・・・・・・・・・