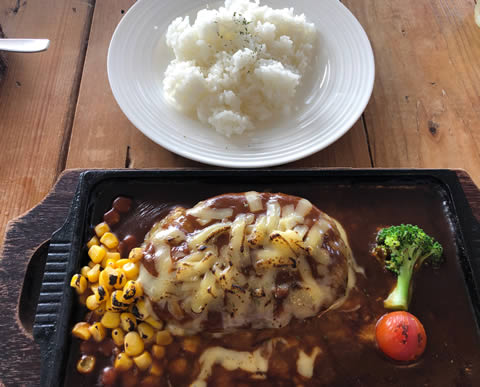ナーシングホームきらら看護の家ではご利用者さんのご要望でたこ焼きパーティーを行いました。
食材を用意してくれたスタッフ。プレートなどを準備してくれたスタッフ。休日でありながらかけつけてくれたスタッフ。料理が上手なおかあちゃん。急遽、たこ焼きの焼き具合が気になり、自宅までたこ焼き器を取りに行ったりなどみんなで力を合わせて楽しみのたこ焼きと焼きそばを食べる事が出来ました。
私もみなさんの様子が見たかったのとどんな感じでしてるのだろう、それと食べたかったので参加しました。
たこ焼きを要望してくれた方はおいしそうに食べていましたし、もっと食べたい!ととても気に入ってたような感じでした。
なんかとても良かったです。
この日は近くの事務所として考えている物件の内覧と能勢に置いているニホンミツバチの巣箱も見に行きました。去年と同じ巣箱にニホンミツバチが元気にいたのでひと安心でした。巣箱は5つ置いていますが、去年と同じ1つしか入っていませんでした。
ニホンミツバチの蜂蜜は採取しません。まずはニホンミツバチが増えてから数年してからその時に分けてもらえればと思っています。
その後に、新しく借りた農地の草刈りを行ったり、雨が予測できたのでそれまでに菊芋の定植なども行ったり、就労継続支援B型で働いてもらうスタッフに畑に入れている麦かすまき、トラクターの運転、玉ねぎの雑草とりなど農作業を行ってもらい、どんな事を行うのか体験してもらいました。
毎日あっという間に1日が終わりますが、喜びが増えていくような種まき・試みは多ければ多いほど良いと思っていますし、そのためには行動あるのみですので、今を大事にがむしゃらに物事を進めれたらと思っています。