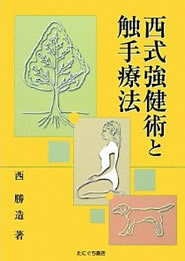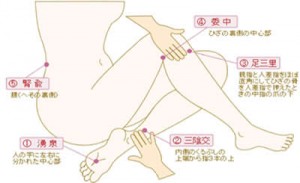柿茶が良い事を知ったのは、2008年にNPO法人がん克服サポート研究会の活動で、肺がんを克服した黒田さんの取材ではじめて知りました。黒田さんは他にも金魚運動・裸療法などの西式健康法を取り入れていました。
そこではじめて西式健康法を知ったのです。
黒田さんは、ご自宅で採れた柿の葉で柿茶を飲まれていたと聞いていましたので、柿茶はビタミンCを摂取するには良いものであり、製法によりビタミンCの含有量が変わってくるという事までは気付きませんでした。
2010年11月に西式健康法の西 万二郎先生と大阪西会の山根会長に取材して
西式健康法の柿の葉茶は、保存中にビタミンCを自ら分解してしまうアスコルビン酸オキシターゼとう酵素の活性をほぼ100%停止させる製法を開発し、採用しているので、自家採取した柿の葉と比べてビタミンCの含有量が違う事を知りました。
民間生薬としての柿葉茶は、タンニン成分による利尿作用などを主な目的ですので、柿の葉を乾燥させてだけのものが多く、ビタミンCも加工、保存中にほどんどが分解されてしまうそうです。
取材以降は、毎月『西式健康法』冊子が届き、西 万二郎先生の連載記事や西式を実践している方の話などを読んだりしています。
その記事の中にビタミンCについて詳しく掲載されていたので記事を要約し抜粋させていただきました。
・・・・・・・ここから・・・・・
合成された純粋体のビタミンCは吸収が早すぎ、消化管から吸収されると同時に過剰分は尿として排泄されてしまい、肝心な血中ビタミンC濃度を高い水準に維持することが困難。それと純粋なビタミンCはかなり酸性度の高い物質なので多量に摂取すると消化管内のPHに与える影響も無視できない。
一方で、野菜、果物、柿の葉茶などの天然物中含まれるビタミンCは、必ず他の成分と混在する形で存在しているので、一気に吸収されず合成の純粋体ビタミンCと比較して徐々に、持続的に吸収される。
・・ここまで要約抜粋しています・・・・・
西式健康法2011年12月号には、大阪西会の山根会長が実践したからし湿布の事が書かれていました。非常に詳細に書かれています。
手当て法の必読書と思っている『家庭で出来る自然療法』東城百合子先生の書籍も見てみましたが、使い方とどのような方が実践したらよいのかのみ掲載されていました。
西式健康法は、だれでも気軽に行える健康法ですし、さらに深く知っていただくためにも『西式強健術と触手療法』という書籍もありますのでお勧めします。会社でも購入し販売予定品です。